
こんにちは。日本腸セラピー協会代表の加藤です。
10月に入り、朝晩の冷え込みが増すと同時に、空気の乾燥も進んでいきます。
中医学では、この乾燥の邪気を「燥邪(そうじゃ)」と呼びます。五行では「金(きん)」に属し、特に呼吸器系を司る「肺」と排泄を担う「大腸」が影響を受けやすい時期とされています。
9月は湿気(湿邪)対策が中心でしたが、10月は肺が最も嫌う乾燥(燥邪)が体調を左右します。
実際、腸セラピーの現場でも「便秘がち」「肌がカサつく」「朝から疲れている」といった声が増える季節です。
今回は、中医学の知恵と腸セラピーの視点を合わせて、10月に意識したい肺と大腸の養生法をお伝えします。
肺と大腸の密接な関係:表裏一体の臓腑
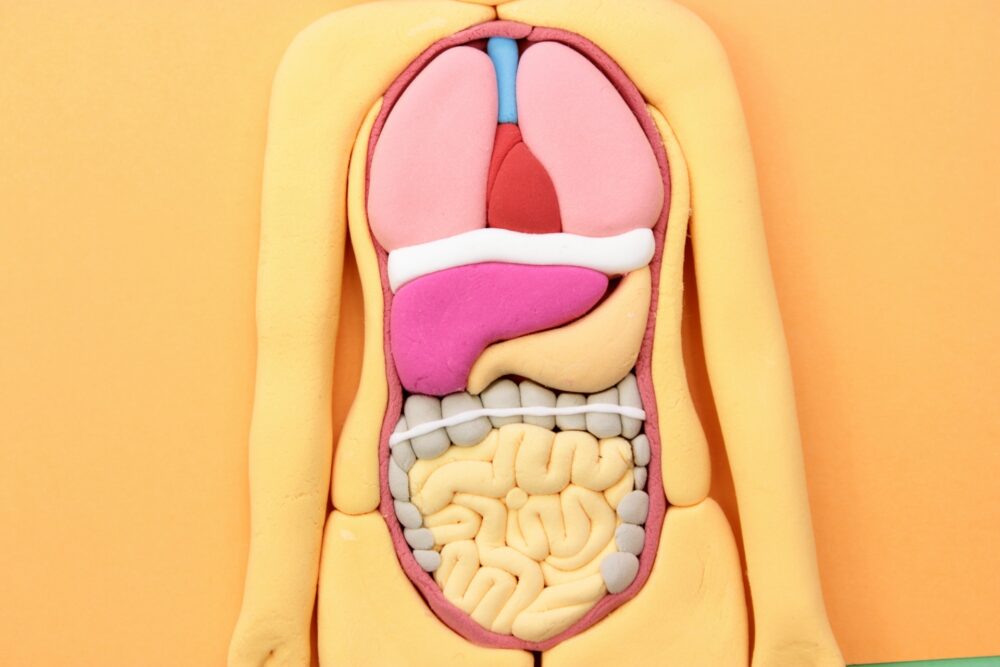
中医学では「肺」と「大腸」は表裏の関係にあるとされ、互いに影響し合います。
- 肺の乾燥:肺は呼吸を通じて全身に「気」を巡らせ、皮膚に水分(津液)を送って潤いを保つ役割も担います。乾燥するとこの働きが弱まり、肌のカサつきや空咳が起こりやすくなります。
- 大腸への影響:肺が潤いを失うと、大腸も便の水分が不足して便秘しやすくなります。逆に、大腸が冷えて働きが乱れると呼吸が浅くなり、鼻や喉の不調につながることもあります。
つまり、お腹を整えることは肺の潤いと全身の気のめぐりを整えることにも直結するのです。
10月に起こりやすい不調のサイン

乾燥と冷えが重なる10月には、以下のような症状が出やすくなります。
- 乾燥による症状(燥邪・津液不足):空咳、喉のイガイガ、肌のカサつきやひび割れ
- 消化・排泄の乱れ(大腸・脾胃の冷え):便秘やお腹の張り、下痢との交互症状
- 全身のエネルギー不足(気虚):朝から疲れが抜けない、倦怠感
- 七情の乱れ:秋は「悲しみ」が肺を弱める感情とされ、気分の落ち込みや不安感が強まりやすい
腸セラピーの施術でも、秋になると便秘と肌トラブルの組み合わせが増えるのを実感しています。
10月の養生ポイント

1. 肺を潤す「白い食材」で潤燥・補気
乾燥に弱い肺には、五行で「金」に属する白い食材や潤いを補う食材が有効です。
- 梨・りんご:加熱してコンポートにすれば体を冷やさず潤い補給
- 大根・れんこん:咳や喉の違和感を和らげる
- 山芋・百合根・白きくらげ:身体の潤い(陰)を補い、肺を助ける
- ごま・豆乳・松の実:女性に嬉しい滋養と美容効果
【ポイント】同じ食材でも「冷やさず摂ること」が大切です。温かい調理法を選ぶことで脾胃(消化器系)を守りながら肺を潤せます。
2. 大腸と脾胃を温める
夏の冷たい飲食で弱った腸は、10月に冷えやすくなっています。
- 朝はおかゆやスープなど温かい食事でスタート
- ごぼう・大根・にんじんなど根菜類や、雑穀米・玄米で腸の動きをサポート
- えごま油やオリーブオイルを少量加え、腸の乾燥を防ぐ
受講生の中には「夜に温かい汁物を加えただけで便通が整った」という声もあります。
3. 時間を意識した養生
中医学では、臓腑ごとに活発に働く時間帯があると考えられています。
- 肺の時間(午前3〜5時):深い睡眠で肺を休める
- 大腸の時間(午前5〜7時):排泄のゴールデンタイム。朝の散歩や水分補給で便通を促しましょう
4. お腹を冷やさない工夫と七情のケア
10月は昼夜の寒暖差が大きく、冷えによる不調が増えます。
- 腹巻きやストールでお腹まわりを守る
- 足首や首元も冷やさないよう意識する
- 入浴は38〜39℃のお湯に15分浸かって体を芯から温める
さらに、悲しみは肺を弱める感情です。朝の深呼吸、自然の中での散歩、音楽やアロマで気分を切り替えるなど、心の養生も忘れずに。
腸セラピーの考えでは「お腹は心の鏡」。お腹を整えることは心を整えることでもあります。
まとめ
10月は乾燥の邪気「燥邪」と冷えが重なり、肺と大腸に負担がかかる季節です。
便秘や肌荒れ、倦怠感はそのサインかもしれません。腸を整えることは免疫力や気のめぐりを高め、家族の健康管理にも役立ちます。
季節に合わせた腸ケア養生を取り入れ、「お腹がよろこぶ暮らし」で秋を健やかに過ごしていただければと思います。
